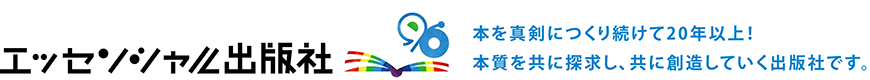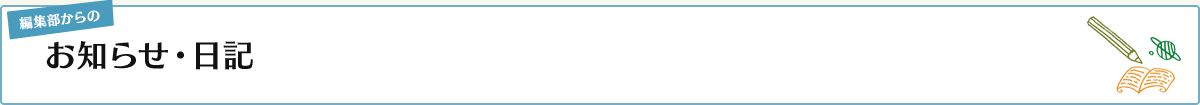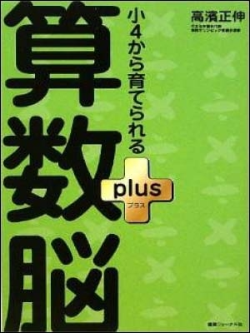【間法物語】
日本語人が古来より持っている「魔法」がある。 それは「間法」。
「間」の中にあるチカラを扱えるようになった時、「未知なる世界」の扉が開かれ、「未知」は、いつしか「道」となって導かれていく。
「間法使いへの道」を歩き始める僕の物語。
【PROFILE】
イエオカズキ 「間」と「日本語」の世界を探求し続けるストーリーエディター。エッセンシャル出版社価値創造部員。
▽小説【間法物語】12 アンコードとエンコード
これまでの「間法物語」はこちら↓
間法物語13
神話の真話
サトルは、先輩のタケルが教えてくれた、神話の話を思い出していた。
「『コンジキ』という神話のこと、サトルは知らないよな?」
「古い昔、日本にあった、『コジキ』とは別のものですか?」
「神話というのは、そもそも、作られたときは、『新話』と呼ばれていて、常に新しい『真話』が、話されていたんだ。昔から、大切なことは、口伝と言って、音だけで話し伝えていくものだったんだ。」
「へえ。そうなんだ。」
「シンワとは、常に変わり続ける話のことをいい、決して文字や本にして、残してはいけないものだった。本にした瞬間、そのシンワは、もはや変化の出来ない死話になってしまうんだ。」
「それなのに、なぜ、人は、本にするんだろうね?」
「それは、シンワの秘密だ。OK。だけど、これだけは言えるのは、シンワの秘密を手にするためには、逆に、ホンが無くては難しいんだ。『本意』を知るためには、『叛意』はどうしても、必要な道具なんだよ。」
その時、タケルの言っていた意味は、サトルにはよくわからなかった。
ただ、そのコトバに、深いメッセージが秘められていることは、ハッキリとわかった。
「コンジキは、今、この瞬間にも書き続けられている、現代のシンワなんだ。」
タケルは、かばんの中から、辞書のような、ノートブックのような、金色の表紙のホンを取り出して、ページをめくりだした。
そこには、沢山の詩が、美しくデザインされていた。そして、その詩の周りには、いろいろな人の手書きの文章が書き込まれていた。
「コンジキは、常に変わり続けるノートブックみたいなもんだから、複数の人の書き込みによって、どんどん進化し続けるシステムになっているのさ。」
そう言うと、タケルは、「コンジキ」の中から、ひとつのページを選び出し、サトルのほうに、手渡した。そこには、こう書かれていた。
ミイラにもミライにも、未来はない。
強いイシを持ち、城壁の前にタテ。
そのとき、魔城は▢になり
バランスジェネレーターになる旅は終わる。
サトルは、資格から死角を見つけ、そこから、魔城へ続く道を発見した。
自分が視覚を使って今まで歩いてきたその道を、今度は、感覚を存分に使って、同じ道を新しい道として、歩いていく。
一瞬でも、自分を見失うと、一瞬にして、あたりは霧につつまれる。
「思いっきり生きたいと思う心が生み出した霧、それが恐怖の霧だよ。 水と蒸気の間に巣食う霧。新しい世界に進んでいくときには、常に、その『間』を通り抜けていくことが必要なんだよ。」
思い切って、その道をゆっくりと感覚を頼りに進んでいくと、ココロのなかに、うっすらと光が見えはじめた。
「勇気と勘。それが、この道を進んでいくための大切なヒントだ。」
勘は感じることが出来る。
頭では考えることは出来るが、感じることは出来ない。
勇気とは、口に出して、言う気持ちだ。
未来がわからないのなら、絶対に未来はつかめない。
なぜなら、わからないのだから、つかみようがないのだ。
未来があるのなら、もはや、未来をつかむ必要はない。
なぜなら、未来はもうあるのだから。
ミライを探してつかんだ瞬間、それは、ミイラになる。
なぜなら、未来はいまだ来ていないのだから。
ミライを決めて創った瞬間、それは、ミイラにはならない。
なぜなら、未来はもう既にあるのだから。
未来はつかむものではない。未来は創るものなのだ。未来はわからないものではない。未来は決めるものなのだ。
「僕は、バランスジェネレーターになる。」という生命への力強い肯定の渇望の隣には、「僕は、バランスジェネレーターにはなれない。」という死に対する力強い拒否の思いが寄り添っている。
思いは、重くなって、自由な気持ちに、重力をかける。
そこに、サトルの隙がある。そこから、恐怖の霧が生まれている。
「おまえは誰だ?」
魔城からの声が、あたり一面に、響き渡る。
恐怖の霧は、音を外側ではなく、内側にこもらせ、人間の耳ではなく、心に、不気味な振動を送り続ける。その振動は、ありとあらゆる不安や怖れにカタチを変え、身体の内部を走り回る。
「サトルです。」
「ダメだな。一体、お前の姓名は何て言うんだよ?」
魔城のささやきは、相手の声色を真似、次第に、心を支配し始める。
「順序が逆なんだよ。」
サトルは、まるでサッチャンが乗り移ったかのように、ハッキリした口調で言い放った。
「最初に、『真』をつかむこと。それが、『間法』だ。 多くの人は、『間』を通して、『真』をつかもうと考える。 だから、『間』は、つかんだ瞬間、『魔』になって、人は、つかんだものに縛られる。 彼らが、『真』にたどり着くことは、決してないのだ。『真』は、『魔』と『間』の接点にある。『間』と『魔』の差を取り払えれば、『真』は自ずから、悟ることが出来る。」
サトルは、『間法』の秘密をつかんだ。
これで、シカクのシステムも、明かされる。
そのとき同時に、サトルは、バランスジェネレーターの資格を得たのだ。
「僕は、差を取り、悟るために生まれてきた、バランスジェネレーターである。」
「 」を外して、僕は叫ぶことにした。
「 」をつけている限り、自分のスタイルは生まれない。
タネおじさんのコトバの通り、もはや、サトルと僕の差も取り払うのだ。
僕は、差を取り、悟るために生まれてきた、バランスジェネレーターである。
世界に音を鳴らすこと、それが大人になることだ。
それが未来を決めるということだ。
「なる」には「なれない」という双子の兄弟が存在している。
「なれない」に目を向けた瞬間、そこには、恐怖が宿る。
「なる」と「なれない」の母がわかった。「である」である。
「自分が何になるか。」ではなく、「自分が何であるか。」である。
「である」には、「なるかならないか」というわからない未来は存在しない。
「である」は、コトバによって、風を止め、未来を決める力がある。
ミイラにもミライにも、未来はない。
強いイシを持ち、城壁の前にタテ。
そのとき、魔城は真白になりバランスジェネレーターになる旅は終わる。
予言どおり、魔の城は、真っ白になった。
そこには、何も描かれていない白紙の未来が残った。
ミイラは、真っ白の包帯を巻いて、内側に、ミライを隠していた。
ミイラは、ミライを育てるためのサナギのような状態だったのかもしれないと、今では、サトルは考えている。
ミライは、ミイラのプロセスの先にあり、ミイラは、ミライだったのだ。
川の流れがせき止められ、ひとつのところに、留まりつづける。
音は鬼になり、イノチはオロチになり、志は死を迎えるように。
せき止められた川の流れは、いつしか、たくさんのところへ、ふたたび流れはじめる。
赤い子供が青い大人になり、芽が花を咲かせ、サナギがチョウになるように。 バランスとは、ただただ、循環し流れている様子。
バランスとは、全ての生命が動き続けているその瞬間。
どこかがせき止められると、バランスは悪くなり、場を乱すことで、また、流れ始める。
バランスとは、ジェネレーターのようなエンジンであり、バランスのいいところとバランスの悪いところがあるからこそ、バランスはとれている。
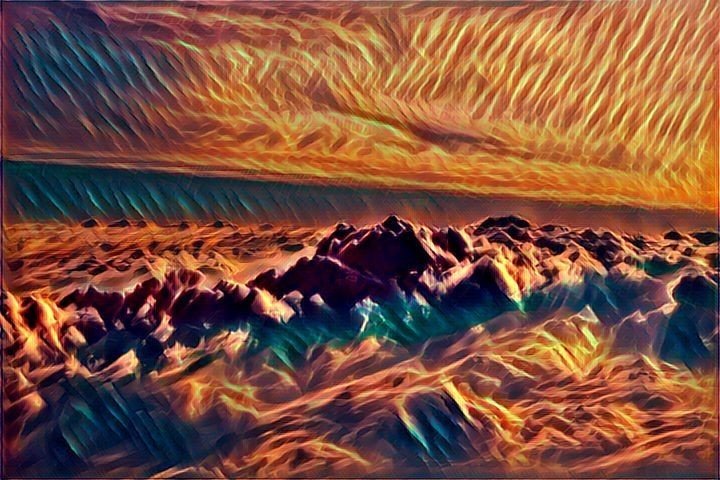
僕もまた、大きな時間と生命の流れの中に生きている。
そのことを知るのでもなく、そのことを理解するのでもなく、そのことを選び、感じる。
(つづく)