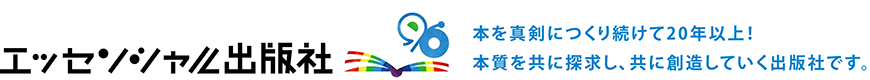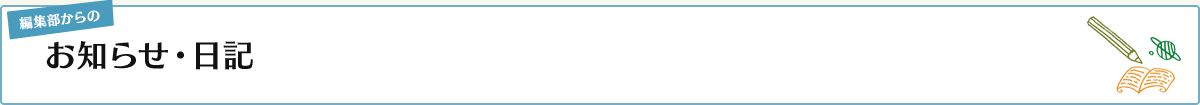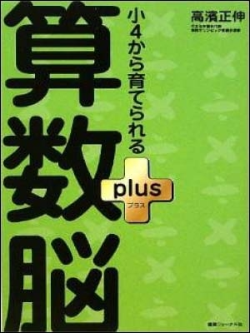『陋巷に在り』で知った「医」の本質
酒見賢一著『陋巷(ろうこう)に在り』を初めて読んだのは、もう20年以上も前のこと。全13巻に及ぶ長編で、中国春秋時代を舞台にしたファンタジー小説です。小説を読む楽しみを、改めて教えてくれた本でもあります。
陋巷とは、裏路地の長屋といったほどの意味で、貧しい人びとが暮らす場所のこと。そこに「在」った(住んでいた)のが、儒教の祖と呼ばれる「孔子」の弟子のひとり、「顔回(がんかい)」という人で、彼が本書の主人公。顔回を通して描かれるのは、孔子が粉骨砕身してその基礎を築いた「儒教」の、その黎明期の姿でした。
「呪術」や「祈祷」といったものが、まだ人びとの暮らしの中に色濃く残っていた時代に、特殊な能力を持った人にしか扱うことができなかった「礼節」や「祭祀」のたぐいを、できるだけ簡素化・形式化することで、人びとに身近に感じてもらい普及させようとしたのが孔子でした。それが、特殊な能力を持つ者たちが末永く生きていくために必要だと、孔子は遠い未来を見据えていたのです。
顔回はそうした孔子の意を汲んで、孔子の夢の実現のために手足となって働いた人です。もちろん、彼も“特殊な能力”の持ち主であり、孔子の行く手を阻もうとする政敵や、魑魅魍魎(ちみもうりょう)のたぐいと戦う“サイキック・ソルジャー”として本書では描かれています。だから、歴史小説ではなくファンタジー小説なのです。
孔子の死後、その言葉を弟子たちが記録した『論語』によると、「顔回ほど学を好む者を聞いたことがない」と孔子は顔回を称賛し、同じ孔子の弟子だった公冶長(こうやちょう)は、「私は一を聞いて二を知る者だが、顔回は一を聞きて十を知る者だ」と述べています。そのたぐいまれなる才能から、孔子をはじめとする一族の中でも一目置かれる存在でした。
ところが、本人は至って欲がなく、じつに質素に生活していて、日々の食べものにも困るような暮らしぶりだったようです。心はいつも市井の人びととともに在る――そんな人物だったのでしょう。本書でもその人柄がしのばれる、なんとも魅力的な好青年です。

購入はコチラ▷Amazon
「医」という文字の成り立ち
この顔回を筆頭に、敵にも味方にも魅力的なキャラクターが何人も登場するがこの本の特長で、なかでも強く印象に残るひとりが、第7巻に登場する「医鶃(いげい)」という人。
字を見ればわかると思いますが、今で言うところのお医者さんです。「お医者さん」なんて書くと「優しい先生」を想像されるかもしれませんが、まったくの正反対。自分を信じるのかと問い、信じられないと答えた相手に対して、「信ずるに値せぬ外道である」と自身のことを揶揄(やゆ)しては不敵に笑うような人物で、ギョロリとした大きな目をカッと見開き、まばたきもせず涙が流れるにまかせて患者を凝視する。そうやってその人の内側を「診る」のです。情け容赦のない冷酷さのある人ですが、その技量には目を見張るものが確かにあって、顔回とは異なるタイプの呪術の使い手です。
いまのお医者さんの中には、患者のことを見もせず、パソコンの画面ばかり見ている人がいるという話をよく聞きます。医鶃のように怖い顔でジーッと見られるのも困るけれど……どちらがよいでしょうね。

前置きが長くなりましたが、第7巻のテーマが「医」です。
このシリーズは、巻頭に白川静先生(漢文学者。漢字の成り立ちを解説する「字統」などの辞書の著者)による、テーマ文字の解説が載っています。それを見ると、「医」は「醫」の略字で、上部の「殹(えい)」は悪霊を祓(はら)う矢の存在を示し、下部の「酉(ゆう)」は酒樽の形だそうです。すべての病気は悪霊のしわざによって起こるため、その矢を使って悪霊を祓って病をいやし、酒樽はのちに酒を使って傷口を清めたり、興奮剤として使ったりしたことから付いたものだと言います。
ここで注目したいのは、矢を使って病気の元となる悪霊を祓いのけるといった呪術的なものと、「アルコール」という現在も医療の現場で使われているものが、古い時代から融合していたということです。要は、「病は気から」という観念的なものと、西洋的な医療とが、いにしえの時代からすでにセットになっていたということに意味があると思うのです。
つづく