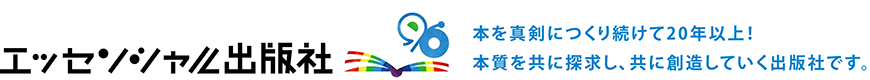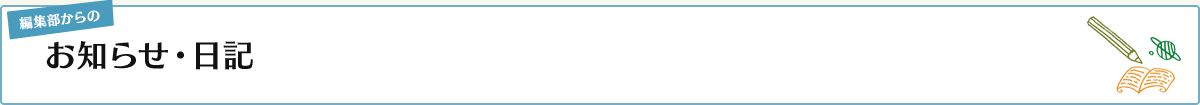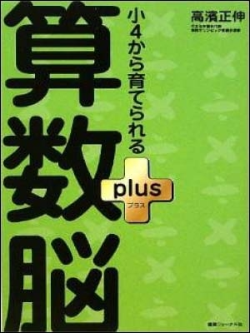▽学校の”面白い”を歩いてみた 〜公立だって、どんどんシフトする。「学びの質」と「職員室」を変えていく
▽学校の”面白い”を歩いてみた②〜「学び」の本質に向き合った時、「教育」も「学校」という概念もシフトする。

古いレールから乗り越えよう。時代は新しいレールへ。
学校の面白いを歩いてみた。
私立学校も、私塾も、地域もチャレンジしている。
公立学校だって、どんどん変わっていく。
「学校」は、今、変わろうとしている。
「学び」の本質に向き合った時、「教育」「学校」という概念もシフトせざるを得なくなってくる。
年齢、地域、分野、性別、時間・・・多くの人が、さまざまな境界線の間で、当たり前のように葛藤し、考え悩んでいる。
価値観を分割する「境界」という線が、その「葛藤」を生み出している。
そこから、ひとつの問いが生まれてくる。
「どうしたら、この境界線を越えられる、心のジャンプが可能なのだろうか?」と。
★
あまりにも当たり前だと考えていたことが、あっという間に変わってしまった時代があった。
そんな時代を、人間は何度も、当たり前のように生きてきた。
江戸から明治という時代にかけても、今を生きることで、未来を築き上げた日本人たちの大いなるジャンプがあった。
その頃、日本は鎖国というシステムに縛られていて、鎖国という「境界」の先に、海外という「世界」があった。その世界を目指して、人々は、政治・文化・経済・人間の鎖国を跳び越え、そこから「明治維新」という新しい時代の物語が数多く生まれた。
坂本龍馬は、藩という制度に縛られていた境界線を踏み越え、日本初のカンパニー、「亀山社中」を作った。そこには、新しい時代のビジネスのエネルギーがみなぎっていた。しかし、今や、多くの人は、その「会社」や「仕事」に縛られている。
木戸孝允は、武士という伝統に縛られていた境界線を乗り越え、「散髪脱刀勝手令」を発布し、ちょんまげを切り、刀を捨てた。その後、ヘアスタイルや背広といった新しいカルチャーが日本を席巻した。しかし、今や、沢山の現代人が、その「西洋的価値観」に、とらわれ過ぎている。
福澤諭吉は、日本語というOSに縛られていた境界線を越え、英語を翻訳して、「広告」や「新聞」をはじめとする、様々な概念を輸入した。そこから、新しいメディアのパワーが台頭した。しかし、今や、日本中が、そのメディアが推進する「競争原理」や「合理主義」に、エネルギーを奪われている。
歴史を振り返り、現在を見たとき、ひとつの疑問が生まれてくる。
「もはや、境界線を越えることは、究極の解決ではないのかもしれない。
結局、シフトしても、繰り返し、新たな境界線が生まれてくるだけなのではないか?」
多くの宇宙飛行士が、口をそろえて言うコトバがある。
「宇宙から見れば、国境など一切なかった。」
地球規模では大きな葛藤を生み出している国境という存在も、宇宙という次元で考えれば、境界線そのものが見えなくなってしまう。
素粒子の研究が進んできて、自然も人間も、自分も他人も、すべてはシンプルな元素の集合体にしか過ぎないことがわかってきた。
ミクロの次元から見れば、今まで人間が様々に分類し、違いを作り出してきた境界線などなくなってしまう。
視点の次元を変えてみれば、時に、世界は簡単にスイッチするのだ。
我々が現在進行形で生きている「withコロナの時代」も、また、あまりにも当たり前だと考えていたことが、あっという間に変わってしまう時代になるだろう。
今、「学校」という枠で取り囲んでいた境界線も、どんどん超えられていく潮流がある。
境界線のボーダーラインで、「学校」という境界線をジャンプする取り組みが始まっているのだ。
★
■インフィニティ国際学院
世界をフィールドに、本質的な体験学習を行う学校。
世界を知り、日本を知り、自分と自分の未来を知る。
100年以上変わらない、日本の教室を飛び出して、世界を旅しながら学び合い、そして自分の生き方を知る国際進路に特化したインターナショナルスクール。
『世界で学べ2030に生き残るために』購入はコチラ▷Amazon
■Loohcs ルークス 高等学院
授業も宿題も定期テストも一切ない。
それぞれの学力や目標に合わせたカリキュラムだから塾に行く必要もない。自分のやりたいことから逆算して授業を選択できる、学生が中心の学校。
先生は学生を応援する存在であり、全て学生が決める。
だから、School→Loochs
無駄な校則、制服は一切ない。
学校行事は学生が創り、校外での活動は公欠扱いになる。
世界をキャンバスにして、校舎から飛び出して、様々な場所で学生生活を送ることができる高等学院。
■ユナイテッド・ワールド・カレッジインターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢(ISAKジャパン)
世界的国際教育機関であるユナイテッド・ワールド・カレッジ(UWC)の加盟校に認定されている、日本で初めての全寮制国際高校。
授業は全て英語、世界中から集まる生徒、社会に変革を起こすチェンジメーカーとして育て上げる仕組みなど、前例のないインターナショナルスクール。
『世界に通じる「実行力」の育てかた はじめの一歩を踏み出そう』購入はコチラ▷Amazon
■アノネ音楽教室
音楽は境界線を越える芸術。
「本物」に触れる、「楽しく学ぶ」。
音楽を通して、本物の美しさに触れることで、国境も年齢も超える、音楽教育の最前線。
子どもを本格的に音楽に向き合わせるには、レッスンが多少つらくても当たり前。プロを目指さない子は大人になって楽譜が読めなくても仕方がない。
日本では標準の、そんなつまらない音楽教育の境界線を超え、楽しさと本格的な音楽教育を共存させる音楽教室。
アノネ音楽教室▷コチラ
笹森壮大(著)『幼児期だからこそ始めたい一生ものの音楽教育』
購入はコチラ▷Amazon
公立学校だって、どんどん面白くなっている!
この本の企画は、エッセンシャル出版社でいまの教育の問題を、あれやこれやと話していたときに生まれた。話せど話せど、話題は尽きない。それほど、いまの教育には問題が山積している。そこから話は、「悪い話しかないの?」という流れになっていった。
教員を目指している若者が多いということもある。
そんな若者たちがいるというのに、教育のブラックな面ばかりに焦点をあてた情報だけを発信していていいのだろうか、と考えた。より良い教育のためには、悪いところを指摘していくことも大事なことだとおもっている。
同時に、明るい前向きな情報も必要なのではないだろうか。
現役の教員にとってブラック的な情報は、自らの仕事の過酷さを再認識し、現状を諦めるためだけの材料にしかなっているかもしれない。しかし明るく前向きな情報は、再度、自分が前を向くための後押しをしてくれるはずだ。自分の職場を変えようという意欲につながるかもしれない。
変わって欲しいとおもうなら、自分たちで変えていくしかない。
教員と話をしていると、こんなに酷い職場だという話をよく聞かされる。
酷い、良くないことが分かっているのなら、「それを変えてみたらどうですか」と質問すると、「誰かが改善の声をあげたら同意しますよ」という返事がかなりの確率で返ってくる。
明るくて前向きな情報は、学校現場を自分たちの力で変えていく実践をしている人たちの話である。そういう話から、自分たちが行動するためのヒントが得られるかもしれない。
保護者にしても、明るい前向きな情報が我が子の教育、学校を考えなおしてみるきっかけになるかもしれない。そんな前提から、明るくて前向きな情報を求めての取材を始めた。
そして、教育を真剣に考えて実践しているたくさんの人たちがいることを知ることができた。
取材してみると、そういう人たち、そういう人たちの周りから聞こえてくるのが、「面白い」だった。
――「学校の面白いを歩いてみた。」前屋毅著「はじめに」より抜粋
前屋毅著『学校の面白いを歩いてみた。公立だってどんどん変わる』
地域ぐるみで校庭に「里山」を作っちゃった学校、いち早く企業と連携してICTを積極的に取り入れている学校、「美術館」という異分子に協力を仰いで朝時間を有効活用している学校などなど、「学び」の質や職員室を変えようと奮闘している各地の学校を訪ね歩いたルポルタージュ。
■目次
●「勉強は面白い」といえる子――モンテッソーリで学んだ女の子
●広島県福山市が挑戦する「分かる授業」
●普通ではない「役立つ」英語の授業をする教員(千葉県柏市)
●変わる教員たち――反発から率先へ(埼玉県所沢市)
●変わる教員たち――対話型鑑賞を教員に広げる試み(愛媛県)
●生徒・児童中心の考えが学校を変える――校則のない学校(世田谷区)
●学校に里山をつくる(横浜市)
●「大事なのは遊び」という世田谷区長
●学校はカラフルでいい(横浜市)
●ファーストペンギンをめざして(埼玉県戸田市)
●変わりはじめた文科省
●教員が授業を決める
――「学校の面白いを歩いてみた。公立だってどんどん変わる」前屋毅著より
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
怒っているような彼の口調が忘れられない。広島県福山市の教育長を務める三好雅章さんの口調には、悔しささえにじんでいるような気がした。
いまの学校の授業では子どもたち一人ひとりの考えや思いは無視され、教員が正しいとするたった一つの答だけにもっていこうとする傾向が強い、とわたしがいったときのことだった。それに三好さんが反対したのではなく、同意して冒頭の発言になったのだ。
子どもたちにしてみたら先生の答だけが正解だとしたら、自分の考えをいってみて違っていたら嫌だから発言しませんよね、とわたしは続けた。それに三好さんが答えた。
「いえるわけないですよ。そして先生の期待する答ばかり探す子どもを、たくさんつくってきたんです」
決まった答しか求められない、教員が主体で子どもたちは無視されている従来の授業を変えようというのが、三好さんの考えであり、教育長として取り組んでいることでもある。
三好さんを訪ねたのは、「従来の教育を変えようと意欲的に取り組んでいる教育長がいる」と聞いたからだった。「変えようとしているのか」と三好さんに訊ねると、それは肯定したうえで彼は次のように続けた。
「いままでの『学力』を完全に否定して次のステージに行けるとはおもっていません。世間の評価というか、社会や保護者の意識は簡単には変わりませんから、全国学力テストのようなところで結果をだす『学力』も避けてとおれないと考えています」
いまさら全国学力テストの説明は必要ないかもしれないが、いちおう説明しておけば、「全国学力・学習状況調査等」というのが正式名称で年に一回、文科省が全国の小学校六年生と中学三年生を対象にして実施しているもので、全国学力テストは一般的な呼び方である。
学力や学習状況を把握・分析して教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てるのが目的だと文科省は説明しているが、自治体や学校の競争の「道具」になってしまっているのも実態である。おかげで、全国学力テストの結果で教員給与や学校予算を決めるといいだす自治体の責任者が登場するまでにエスカレートしてしまってもいる。
いろいろ問題があるとしても、そうした学力を否定するのに三好さんが必死になっているわけではない。わかりやすい学力で結果をだすことは、保護者をはじめとする世間に説明しやすいし、納得してもらいやすいのも事実である。
現役の教育長として、その事実は事実として受けとめなければならないのだろう。ただし、全国学力テストに代表されるような学力競争を彼が全面的に支持しているわけでもない。全国学力テストの成績の悪い学校の教員給与は引き下げるし、学校予算も減らすと脅しをかけるなんてことをやろうとしているわけでは、もちろんない。
彼が変えようとしているのは、もっと根本的な問題である。それは従来の教育がかかえている、かなり深刻な問題でもある。
「答はだせるけれども分かっていない、これが従来教育の最大の問題なんです。テストの点数が学力ではない、という前提からスタートしました。そこから考えていくと、テストで点数はとれているけれども、子どもはほんとうには分かっていない、ほんとうには学んでいないことが分かってきました」その例として三好さんは、小学生の読解力についてふれた。
『AIvs.教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著 東洋経済新報社)という本が「中高生の多くが中学校の教科書の文章を正確に理解できていない」ことを明らかにして話題となりベストセラーになっているが、その本が出版される前の二〇一七年に福山市教育委員会は市内の小学校一年生二クラスの個人を対象に調査を行い、小学校一年生の終わりごろから文章が読めないことに気づいていた。
「足し算も引き算もできるし、ひらがなも読めている。ところが三行くらいの文章になると、もう意味がとらえられていない。意味が分かるのは、クラス全体の三割くらいしかいないんですよ」
そこで教室での子どもたちの様子を見ていると、「なんだか、つまらなそうにしている」と三好さんは気づいた。三行の文章が読めないのでは、教員の話が理解できるわけがない。授業の内容が分からないのだから、面白いわけがない。
「それでも先生は一方的に話をすすめて、教えているつもりになっている。この画一的な一方通行のスタイルが、従来の学校での授業なんです」
それでも、テストでは点数をとれる。授業の内容を理解していなくても、教員の期待する答、つまりテストにおける答は探せるからである。もはや、テクニックである。
全国学力テスト対策で過去に出題された問題(過去問)を子どもたちにやらせることが全国的に行われているが、それもテクニックを覚えさせているにすぎない。福山市だけではなく、日本の教育そのものがテクニック優先になっていたのかもしれない。
「これではいけない、と考えました。分からないのに点数だけとれる教育ではいけない。子どもたちがほんとうに分かる授業をしなければ、子どもたちが成長していくことにはならない」と、三好さんはいった。そして福山市教育委員会が二〇一八年から掲げたテーマが「学びは面白い!」だった。教室でつまらなさそうにしていた子どもたちが授業を面白いとおもう、そんな教育に変えていこうというわけだ。
「学びって面白いんですよ。赤ちゃんは、誰が教えるわけでもないのに、主体的に意欲的にどんどん言葉を覚えていくじゃないですか。面白いからですよ。それが学校にはいったとたん、教科書どおりに、教員が一方的に教えだす。子どもたちの主体性も意欲も無視されてしまう。面白いわけないじゃないですか。主体的で意欲的な授業にすれば、面白い授業になるし、授業の内容を子どもたちもほんとうに分かるようになります。
ほんとうに子どもたちが分かって、その結果として全国学力テストなどの成績が上がるなら、それはそれでいいとおもいますよ」
小学校では二〇二〇年度から中学校では二〇二一年度から本格的に実施される新学習指導要領で文科省は、「主体的・対話的で深い学び」を打ち出している。ご存知のように当初は「アクティブ・ラーニング」という言葉を使っていたが、「分かりにくい」という意見が多かったのを受けて日本語に変えた。それで分かりやすくなったとはおもえないのだが、ともかく「主体的」という言葉を使ったのは、従来の「教え込む教育」を文科省も反省しているからではないのだろうか。そう、おもいたい。
封建的ともいえる学校運営の弊害
ともかく「主体的・対話的で深い学び」とは、子どもたちが主体性をもって意欲的に学ぶことを目指しているはずである。それなら福山市のような「面白い」などの表現してくれたほうが、明解とまではいわないが、ずっと馴染みやすいとおもったりもする。
福山市教育長の三好さんは、「つまらない授業」を「面白い授業」に変えて、「分からなくても点数をとれる子どもたち」から「分かったうえで点数のとれる子どもたち」に変えようとしている。暴力的な従来の教育を変えようとしているわけだが、ただ、そうそうスンナリと変えられないのも現実のようなのだ。
福山市の教員に実際に会って、「学びは面白い!」について訊いてみた。たくさんいる教員の感想や意見がまったく同じわけはないのだが、このとき会った教員はけっこう否定的な見方をしていた。
「従来の教育を変えるといっていますが、三好教育長が辞めたとたん、以前に逆戻りする可能性だってじゅうぶんあるわけですよ。それを考えると、三好教育長がいうように変わっていいのかどうか、おおいに迷いますよ」
といったのは中学校の教員だった。彼のいうことにも、もっともな理由がある。
事情を聞けば、「なるほど」とおもわざるをえないほどの理由だ。
福山市をふくむ広島県は「厳しい管理教育」を徹底してきた土地柄でもある。それについて説明してくれたのは、小学校に勤める教員だった。
「学習指導要領で決められた時限数を厳守するために、授業でやるべきことを教育委員会が決めて、それを各校長に降ろしてきます。それを校長は校長権限で教員に強制するわけですが、それに対して先生が意見を述べるなんていっさい認められていません。職員会議も会議とは名ばかりで、上で決まったことが伝えられるだけの場でしかなくて、先生が意見を述べて議論するなんて余地はまるでありません」
授業の内容についてはさらに厳しく決められてきたという。それを、わたしは呆然としながら聞いた。
「授業を始めるときは、まず先生が、その時限の狙いを必ず黒板に書くように決められています。そして授業時間内に決められた内容をきっちりこなし、最後には『まとめ』を生徒に示さなければいけません。このとおりにやらなければならないし、違うことをやってはいけません」
ファミリーレストランのマニュアル的に厳しい。もしかすると、それより厳しいかもしれない。がんじがらめで画一的な授業方法だから、子どもたちの主体性とかが入り込んでくる余地など皆無である。そんなものをいれていたら、最後の「まとめ」にまで到達できないし、それが見つかれば大目玉をちょうだいすることになるのだから、教員は「マニュアル」をこなすのに必死にならざるをえない。時間内に終わらせようとすれば、当然ながら「教え込む」というスタイルにならざるをえない。
そんな授業だから子どもたちが面白いわけがないし、つまらないはずだ。意欲なんて湧いてくるほうが不思議というものだ。それでも子どもたちは、テストになれば点数だけはとれる。最後に「まとめ」があるからだ。それこそ教員が期待する、そしてテストが期待している答であり、「まとめ」さえ覚えておけば、過程は分からなくても点数はとれる。点数はとれるが、ほんとうに大事なことは分かっていないことになるし、学ぶことの面白さなんて無用のものでしかない。
広島県にかぎらず、ここまでではないかもしれないが、日本中の学校で似たり寄ったりの授業が行われている。それが、従来の教育なのだ。広島県でも最近では緩んできているというけれど、こうした従来の教育がずっと行われてきただけに、簡単には変わらない。なによりも、そういう授業スタイルに教員も慣れきってしまってきているのだから、変えるとなれば簡単にはいかない。
それを福山市教育長の三好さんは、一八〇度といってもいいくらいに変えようとしているわけだ。それに従って大転換したはいいが、教育長が代わって「元に戻せ」となったら現場の教員にとっては大混乱そのものの状況となってしまう。教員の立場になって考えてみれば、心配でしかたないのもうなづけないではない。
ただ問題は、教員自身が従来の教育がいいのか、三好さんが目指しているような教育がいいのか、ということである。三好さんの目指す教育を支持するなら、三好さんが教育長を辞めたあとも、それを続けていけばいい。従来の教育がいいとおもっているのなら、三好さんがなんといおうと従来どおりの教育を続ければいいのだ。
教育長が自ら教壇に立つ!
それには、三好さんがやろうとしている教育の内容を分かっていなければならない。どういうものか分かっていなければ、肯定も否定もできないはずだ。そこで三好さんが教育長としてどういう教育をやろうとしているのか、どのように現状を変えていこうとしているのかを、どう教員として解釈しているのかを訊いてみた。
「教育長はいろんなことをいってるみたいですが、なにをやろうとしているのか、さっぱり分からないんですよ」
中学校教員が答えた。隣で聞いていた小学校教員も、しきりにうなづいている。彼も、教育長の考えていることを理解できていないようである。中学校の教員が続けた。
「教育長が目指す授業のモデルみたいなビデオを観たことがあるんですが、子どもたちがワーワー勝手にしゃべっているだけで、なにをやりたいのか、さっぱり分からない授業でした」
そのビデオは、三好さん自身が授業をやっているものだとおもう。同じかどうかわからないが、三好さんは学校をまわって自らモデル授業をしているのだが、そのひとつである小学校二年生の教室での三好さんの授業の様子を映したビデオをわたしも観てみた。
中学校の教員が指摘したように、「ワーワー勝手にしゃべっている」ような様子が映しだされていた。ただし朝食のメニューについて話している子もいれば友だちの悪口をいっている子もいるといったような「勝手」ではなくて、授業のテーマに沿って三好さんが質問したことに対して、それぞれが自分の考えに基づく答を口にだしている光景だった。その次には、「今度は手を挙げて一人ずつ発表してみようか」という三好さんの言葉が続いていく。
従来の授業からすれば「行儀が良い」とはいえないだろうし、「きちんとした」ともいえないのかもしれない。しかし、教室のほとんどの子が授業のテーマについて、いっしょうけんめい語っている。自分の頭で考えて、それを口にしているのだ。
「先生が期待している答ってなんだろう」とか「正解はなんだろう」と考えて発言しているようなためらいは、まったく見うけられない。自分の頭で考えたことだから一刻も早く口にしたいという気持ちが「ワーワー」になっている、いっしょうけんめいさが伝わってくるようだった。子どもたちにとっても、とても面白い授業なのではないだろうか、ともおもえた。
その光景を観ながら、インタビューのときの三好さんの話を思い浮かべていた。それは中学一年生の国語の授業を彼がやったときの話だった。「説明文」をあつかう授業で、そこで使われた教材はすごく難しい内容だったという。まず三好さんは、「従来の授業」のスタイルを解説した。
「中学一年生の学力はバラバラで、その教材を読めない子もいれば、読めても意味をとらえられない子もいるはずなんです。でも教員は、いわゆる『説明文の指導の仕方』に則してやっていくわけです。教員が文章を一度読んで、段落を確認して、その要旨を子どもたちにまとめさせる、といったぐあいです。
要旨をまとめさせるためにグループに分けるんですが、そのグループでもまとめるのは一人か二人しかいない。そして、その子たちが発表する。ほかの子はというと、ただジッとしているだけです。
なんとなく子どもたちが主体的・対話的に学んでいるようにみえるんだけど、実は三分の二以上の子どもたちは何も考えていないし、話し合いに参加もしていない。ただ、『お客さん』として座っているだけです」
どこでも、こんな授業風景があふれているのではないだろうか。行儀よさそうにみえて、実はやる気のない、つまらなそうな子どもたちの顔までが目に浮かんできそうだ。三好さんの授業だと、これがどうちがってくるのだろうか。
「私が担当した時限では説明文の『要旨をまとめる段階』だというから、まず『要旨って何なの?』って子どもたちに質問しました。すると、いくつか答を口にする子はいました。次に『それを、どうやってみつけるの?』って訊きました。それにもポツポツと答は返ってくるんだけど、活発な発言が飛び交うまでにはならなくて、そのうち沈黙が流れ、それが続くんです」
これも、ありがちな授業風景なのではないだろうか。誰もが気まずい気持ちなのだが、かといって口を開けない。そういう重苦しい空気が教室を圧迫しつつあるのを誰もが感じ、ジッと耐えている。
「そういうときに従来の授業だと、まず口を開くのは先生なんです。先生は沈黙がたまらんから、すぐ先生が答を教えてしまう」
うん、うんとうなづいてしまう。みんなが黙るなかで、「しょうがないな。教えてやるから、しっかり覚えときなさい」といわんばかりの態度で教員が答のようなものを口にする。そんなことを、わたしも経験してきたような気がする。
「でもね、子どもたちが黙っても、私のほうから口を開くようなことはしません。黙っていても、子どもたちが頭のなかで考えていることは分かっているからです。考えているにもかかわらず、『答はこれよ』と先生が先にいっちゃうと、子どもたちは考えるのを止めてしまうからです。考えるのを中断されて答を教えられても不快感ばかりで答は印象に残らない、だから学ぶこともしない」
これまでの授業、教育における「落し穴」的なものを三好さんにズバリといわれてしまった気がした。だから、従来の授業は面白くなかったのだ。面白くないから「分かる」にもつながらないし、どんどん「分からない」だけが積み重なっていくことになる。なおさら面白くない三好さんは続けた。
「黙っていても、そのうち誰かが口を開くんです。それに『いいね』と応えると、それとは違ったことを考えていた子は『自分のは正解じゃなかったんだ』とおもってしまいますから、『ふーん』など否定も肯定もしない返事をしていると、否定されないことがわかって意見を口にする子が増えてくる。
それにヒントを得て違う意見もでてくるし、突飛な発想の答もでてきます。それもヒントになることもあるし、そんなことをいってもいいんだというので次々と意見がでてくる。そうやって自分の頭で考えていると、分からないこともでてくるから、隣の子に訊ねてみたりするんですよ」
見方によれば、これは「ワーワー」にしか見えないかもしれない。しかし子どもたちは自分の知識を総動員しながら考えているし、ほかから知識を吸収している。つまり、学んでいるのだ。
「そうやって学んだことは印象深いから忘れませんよ。自分のものになる。それなのに従来の授業は、せっかく子どもが考えているところを上から蓋をしてしまっていた」
そういう授業を止めようと三好さんはいっている。しかし従来の教育、授業に慣れてしまっている教員がすぐに受け入れることは難しいことでもある。特に厳しすぎる管理のなかで従来の教育を実施することを強要されてきた福山市の教員にとっては簡単なことではないし、不安もある。
「だから、私がモデル授業をやって、こういう方向を目指していることを観せているんです」
と、三好さんはいった。教育長である彼が学校で授業をやっているのには、そうした理由があったのだ。そのために彼は、マメに学校に足を運ぶが、それが何の前ぶれもなしの訪問なのだそうだ。突然の訪問なのだが、もちろん「抜き打ち検査」なんかのためではない。
教員との距離を縮めたい
「私は県の教育委員会で一〇年、市の教育委員会で八年勤めました。それから校長を一年三ヶ月やったんですが、そのとき初めて学校側として教育委員会の人たちを迎える立場になってみて、ほんとに衝撃的でした」
どう衝撃的だったかといえば、教育委員会の人間が来るとなると学校側としては準備万端整えて待つ態勢になっていたからだ。教育委員会を迎えるときの顔と、普段の顔があまりに違うことに衝撃をうけたのだ。
それは企業でも同じである。工場や店舗に社長が来るとなると、それこそ天地がひっくり返るような大騒ぎをして準備する。店舗では、社長に対して粗相があってはいけないと、社長の通るところから顧客を排除してしまう、などということも普通にあるらしい。それと同じことを、学校でもやっているわけだ。
「普段の様子をみないことには、教育長として何を守り、何を変えていったらいいのか判断を誤ってしまうことになるでしょう。だから私は突然に学校に行って、普段の様子を見ようとしているんです」
三好さんはいった。さらに突然の学校訪問には、もうひとつの目的がある。それを彼は、「教員と近い距離で話すため」と説明した。教育委員会が訪問するというと大騒ぎするくらい教育委員会と学校のあいだには距離があるのだから、教育委員会と教員個人となったら、さらに大きな距離があると考えられる。実際に大きな距離があるのだ。
先ほど教育長が何をやろうとしているかわからない、といった中学校の教員に、「それなら校長や教育委員会に訊ねてみればいいんじゃないですか」といってみたところ、「校長も分かっていないから訊いても答は返ってこないでしょうし、市の教育委員会だって手探りでやっているところでしょうから、訊いてみたところで分かりませんよ」という返事が返ってきた。
最初から訊いてみる気さえない。距離が遠いのだ。三好さんが続けた。
「私がやろうとしていることを校長に伝えても、そこで止まってしまうこともあります。だから現場の先生と直接に、気軽に話せるようになれば距離も縮まって、理解してもらえるのではないかとおもっています。だから、事前に連絡しないで学校を訪問しているんです」
その一貫で、自ら授業をやって、「こういうことをやりたいんだ」と現場の教員たちに伝えようとしている。とはいえ、まだ始めて間もないし、それこそさかのぼれば明治時代からの教員が一方的に教え込む従来の教育、授業のスタイルを簡単に変えられるわけもない。それは、三好さん自身も分かっているようだ。
「私の授業を観てもらっても、直接話すようにしてみても、もちろん研修もやったりしていますが、すぐに全部の先生方に理解してもらえるとはおもっていません。戸惑っている先生も多いでしょうね。だからこそ私も、地道に学校を訪問する活動を続けなければとおもっています」
ただ、三好さんが孤立無援の闘いを疲労困憊しながら続けているわけでもない。「私のやろうとしていることを理解して、納得して、それで実践している先生は増えてきています。そういう人たちを応援して、そんな先生の授業を多くの先生たちが自分の目で観ることで、さらに広がっていくだろうという実感はもっています」と、三好さんはいう。
子どもたちが自分の頭で考える授業に変わってきた!
福山市立霞小学校校長の高橋裕美子さんが「全員ができているわけでなく、教員によっての温度差はありますけどね」と前置きして、次のように話してくれた。
「跳び箱の授業を見学していたときのことなんですけど、まずは子どもたちに跳ばせて、それから見本のビデオを観せるんですが、従来どおりであれば、それを先生が説明して、そして『こうやりなさい』と教えるんですね。ところがその授業では、教員が説明するのではなくて、『どうしたら、うまく跳べるか』を子どもたち同士で話し合わせているんです。自分が跳んでみた経験とビデオを比較しながら、どこが違っているのか、どうしたらいいのかを、いろいろ意見をだしあって話し合っていたんですね」
それから、再び跳びだすのだが、その光景も高橋さんにしてみれば意外なものだったという。跳び箱の上にはビニールテープで線が記されていたが、それも彼女の「常識」からすればちょっと違っていたそうなのだ。
「従来なら、引かれてある線は一本だけです。その線を示して先生は『ここに手をつきなさい』と全員に同じ場所に手をつくように教えるわけです。ところがその授業では、赤、青、黄の三本の線が引いてありました」
三本もあれば、「どこに手をつくか」を教えるのは難しいはずである。一本だから「ここ」と指示できるが、三本では、どんなときに青だったり赤だったりするのか、教え方が複雑になる。そんな複雑な説明を教員がしたら、子どもたちは混乱してしまうにちがいない。同じように高橋さんもおもったようだ。ところが、目の前で始まった光景が予想とは違うものだった。
「どこの線に手をついたらうまくいくのか、一人ひとりについて子どもたち同士がアドバイスしながら探っているんです。ビデオの見本とも比べているとおもうんですが、『黄色のほうがいいかもしれない』といってから跳ぶのを見て、『やっぱり赤だね』といったぐあい。跳んでる子も『赤のほうが跳びやすいみたい』と自分の感想をいって、話し合ってるんです」
これも見方によっては、ただワーワーいってるだけの光景にしか見えないかもしれない。しかし高橋さんにも、ワーワーいって子どもたちが授業をサボっているわけではないことは、すぐに分かったという。
「同じクラスといっても、体格も違えば身体能力も違います。そんな子たちが跳び箱を跳ぶのに、同じ線でいいわけがないんですね。『ここ』って一本の線だけを押しつけるほうが無理があるのです。
三本と選択肢が増えると、個人に合わせた跳び方ができます。
そのほうが自然ですよね。
ぼくは赤い線が跳びやすかった!
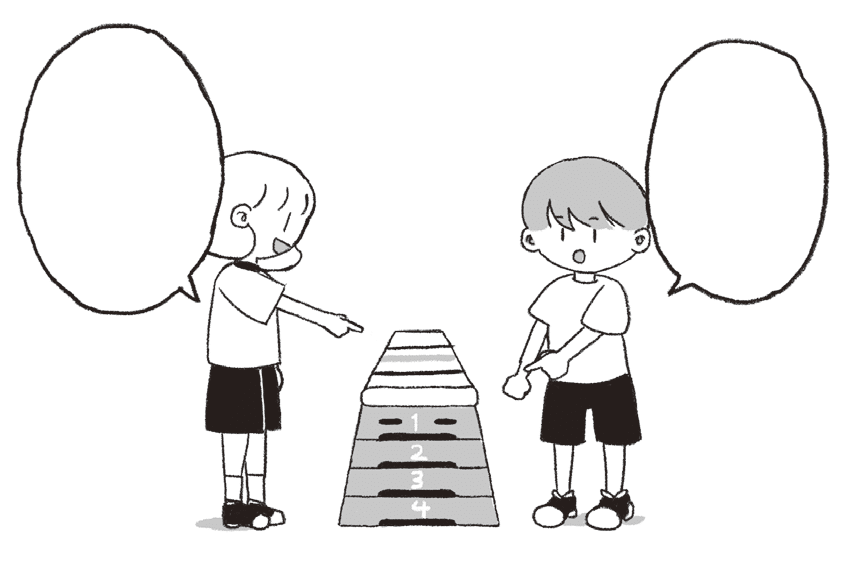
わたしは今度、黄色い線でやってみる。
どれを選ぶか子どもたち同士でやっているわけですが、無責任にやっているわけではありません。どこの線に手をつけばいいか、自分の経験やビデオの見本、なにより目の前の友だちの跳ぶ様子をまじえて考えて結論をだしてアドバイスしているわけです。
いっしょうけんめい考えている。その考えたことは、もちろん友だちのためになっているんですが、自分のためにもなっているはずです。考えたことが、次に自分が跳ぶときに生かされるわけです。知識と経験がほんとうに身についていると感じましたね」
さらに高橋さんは、子どもたちが何回も何回も跳んでいる姿に、『あの体力だけでもすごいな』とおもったそうだ。教員に強制されていては、何回も跳ぶ気にはならないかもしれない。自分ではシックリこないにもかかわらず手をつく場所を決められてしまっていては、なおさらだ。自分の考えを求められて、そこから工夫を重ねていって、やってみる。
子どもたちにしてみれば面白いにちがいない。面白いからこそ何回も何回もやれるし、だから身にもつく。「教育長のいっていることをちゃんと実践できる先生がでてきているんだなと実感しましたね」と誇らしげにいって、さらに高橋さんは事例をあげた。
「六年生の音楽発表会の練習を観に行って、『もうちょっと、こうしたらどう?』って私がアドバイスしたんです。そうしたら担任の先生は、自分が指示するのではなく、『いまいわれたことを、みんなで話し合ってみて』っていったんです」話を振られてすぐに反応が返ってくればいいのだろうが、なかなかそうはいかず、子どもたちは口を閉ざしたままの状態となる。沈黙が流れるのだ。
「それでも担任はジッと待ってるの。私のほうが『時間がないのに大丈夫かしら』とヤキモキするんだけど、担任はジッと待ってる。私もそうですけど、教員は沈黙に耐えられないんですよ。教室がシーンとしている状況は苦痛でしかないので、自分が引っ張りたくて我慢できなくなるものなんです」
もちろん子どもたちはダンマリを決め込んでいるわけではなく、頭のなかで考えているから、表向きには沈黙となるのだ。その子どもたちの思考を止めないために、担任の教員はジッと待っている。そのうち、ポツポツと意見がではじめ、話し合いになっていったそうだ。
「教育長がいっていた子どもの思考を邪魔しないって、こういうことなんだ」と、高橋さんも気づかされたという。
教育長の三好さんのいう「教育は面白い!」を理解して実践する教員が徐々にではあるけれど増えているのも事実のようだ。さらに広まっていけば、福山市の教育は教員が一方的に教え込む従来の教育から大きく変わっていくかもしれない。面白いからこそ分かって身につく、ほんとうの学力を子どもたちも手に入れることになるのだろう。