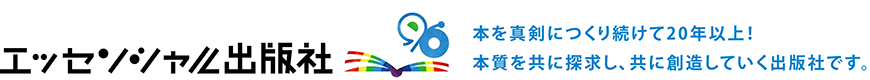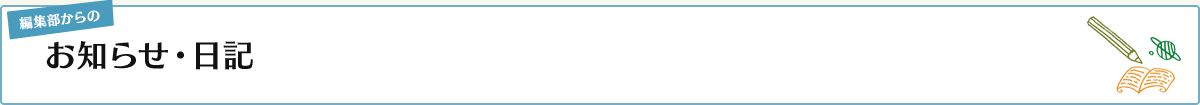【間法物語】
日本語人が古来より持っている「魔法」がある。 それは「間法」。
「間」の中にあるチカラを扱えるようになった時、「未知なる世界」の扉が開かれ、「未知」は、いつしか「道」となって導かれていく。
「間法使いへの道」を歩き始める僕の物語。
【PROFILE】
イエオカズキ 「間」と「日本語」の世界を探求し続けるストーリーエディター。エッセンシャル出版社価値創造部員。
▽小説【間法物語】10 ヒミツのヒミツ
これまでの「間法物語」はこちら↓
大人になる旅
22歳の誕生日、僕は、ついに、大人になる決心をした。
ついつい、忘れていた。
大人には、自分の意志でなる必要があるのに。
大人には、自然になるものだと勘違いしていたのだ。
勘違いよりも、もっと深刻な間違い。
すべては、音違い。
名前の音を鳴らすことで、大人に『鳴る』ものだったのに、 肩書きが大人になることで、「なるようになる」のかと思いこんでいた。
今まで、僕は、自分がもらっている『音』に感謝をすることはなかった。
僕は、とんでもない『恩』知らず野郎だったのだ。
『成る』と『鳴る』・・・ここには、イシがあるかないかの違いがある。 『鳴る』ためには、『イシ』が必要なのだ。
僕の持っている、そのイシは、鏡のように透き通っていて、 自分を、まるっきりそのまま映し出してくれる水晶のようなイシだ。
それは、ちょっとしたキッカケだった。
僕がある箱を手にするチャンスから、それは始まった。
魔城のシステムでは、『資格』を取ることによって、『視覚』を奪われてしまう。
思いっきり生きていくためには、どうしても必要不可欠なものように思わされてしまうプログラムが、『資格』という『四角』の箱自体にセットされていた。
しかし、一旦、その箱を渡されてしまうと、もう、世界を自分ではつかむことは出来ない。
システムは、『四角』の箱を手に出来る、様々な『資格』を沢山用意していて、あたかも、ひとりひとりが自らの意志で選んだように感じる、誘導プログラムを発動させる。
僕が偶然手にしたのは、美しくて、光り輝き、誰もが欲しがる、人気のある箱だった。
当然、僕も、長い間、欲しくて欲しくてたまらなかったので、その箱の資格を手にしたときは、嬉しくて飛び上がりたいほどだった。
だけど、周りの仲間も、口々にスゴイスゴイと誉めてくれるものだから、逆に僕の中の偏ったものに対する嫌悪感が発動してしまったのだ。
「そんなに、皆がいい、いいって言う、いいものだったら、嫌だなあ。 だって、そんなの皆と同じじゃないか。」
そう思って、『四角』の箱を覗いていたときに、たまたま、『視覚』の『死角』に気づいてしまったのだ。 その死角には、『魔城』システムの暗号コードがひっそりと隠されていた。

そう、僕は見つけてしまったのだ、システムの暗号を。 そう、そして、そこには、もっと驚くことに、僕がずっと探していた『間法』の記号も働いていた。
(つづく)